北海道斜里町と羅臼町にある、オホーツク海の南端に突出した半島です。長さ約70km、基部の幅が25kmの狭長な半島であり、西側の斜里町側がオホーツク海、東側の羅臼町側がが根室海峡に面しています。また、半島東側には国後島が平行する形で横たわっています。
名前の由来は、アイヌ語の「シレトク」(地山の先、あるいは地山の突き出た所)を意味しています。
半島中央部に最高峰の羅臼岳をはじめとする山々(知床連山、知床連峰)があり、一部に海岸段丘が見られるほかは稜線から海岸まで平地がほとんど見られない急峻な半島となっています
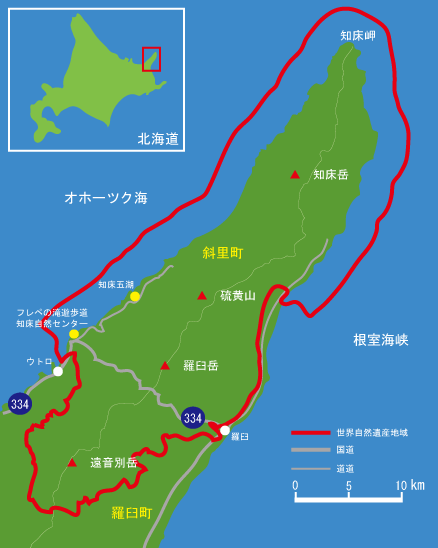
冬は砕氷船として使われています。ツアーではほぼこの観光船に乗ります。
不穏に空で、途中で中止になりました。(H24)
この年は短いコースでした。(H18)
知床半島の海岸は、冬の荒波や流氷に削られるため、ほとんどの場所が岸壁になっています。川が流れ込むところは岸壁が切れるためそんなところによくヒグマが現れるそうです。ただ、船の上からなら見たいのですが、まだ一度も出会っていません。(H24)
高さ約100メートルの断崖の割れ目から染み出した水が涙の雫のように斜面を流れ落ちる様子から「乙女の涙」という愛称で親しまれている。(H24)
川からではなく染み出しているのでいつも水量は少ないです。(H18)
このように岸壁が切れているところはヒグマ観察ポイントです。(H18)
ここは川が流れ込んでいます。この上流にカムイワッカ湯の滝があります。(H18)
半島の先の方まで見えています。この年は天気がよかったのですが、短いコースでした。(H18)
山頂が尖っているのが、いつか行きたいと思っている憧れの知床硫黄岳です。(H18)
右端が羅臼岳、順に、三峰岳、サシルイ岳、オチカバケ岳になります。(H18)
